Linux標準教科書の第12章を読みました。
章末テストの解答と解説を自分の言葉でまとめます。

この記事を書いているぼくは実務経験1年。独学で未経験から従業員300名以上の自社開発企業へ転職しました。実務ではVue.jsとRailsを毎日書いています。
第12章の章末テストの解答・解説
(1) マシンのハードディスクのパーティションを確認するコマンドを記述しなさい。
この問題は記述式です。
解答・解説
正解は「fdisk -l コマンド」です。
(2) スワップファイルシステムについて説明しなさい。
この問題は記述式です。
解答・解説
正解は「プログラムやデータを読み込むための空きメモリ領域がなくなった場合に、Linuxのカーネルがその時点で利用していないメモリ上のプログラムやデータを一時的にディスク領域へ退避するしくみ」です。
(3)ext3 や ext4 が ext2 より優れている点を 1 つあげなさい。
この問題は記述式です。
解答・解説
正解は「ジャーナリング機能を持つ点」です。
ジャーナリングはファイルシステムに対する書き換え処理のコマンドをファイルシステムに記録する機能です。
この記録があることでシステム障害時が発生した場合でもデータの整合性を保ち、迅速な復旧が可能となります。
(4) ハードリンクとシンボリックリンクの違いを説明しなさい。
この問題は記述式です。
解答・解説
正解は「ハードリンクは参照したいファイルの実体を直接指して共有するのに対し、シンボリックリンクはそのファイルが保管されている位置を示す擬似的なファイルを作る」です。
ハードリンクを削除しても、参照元のファイルは削除されません。
シンボリックリンクはWindowsにおける「ショートカット」と同じ考え方の概念です。
(5) ログインしているユーザのホームディレクトリの使用量を表示するコマンドを記述しなさい。
この問題は記述式です。
解答・解説
正解は「du -sh ~」です。
du コマンドに -s オプションをつけると指定したディレクトリの使用量やファイルのサイズを調べることができます。
さらに -h オプションを付与することで、人間が読みやすい単位(KB, MB, GBなど)でデータ量を表示してくれます(つけない場合はバイト単位で表示)
おわりに
Linux標準教科書の章末テストが全て終了しました。
Linuxの基礎は学べたので次のステップへ進みます。
技術書が好きなエンジニア向け
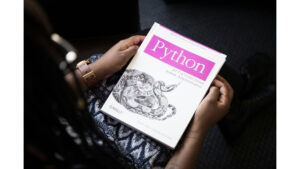
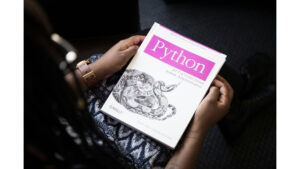
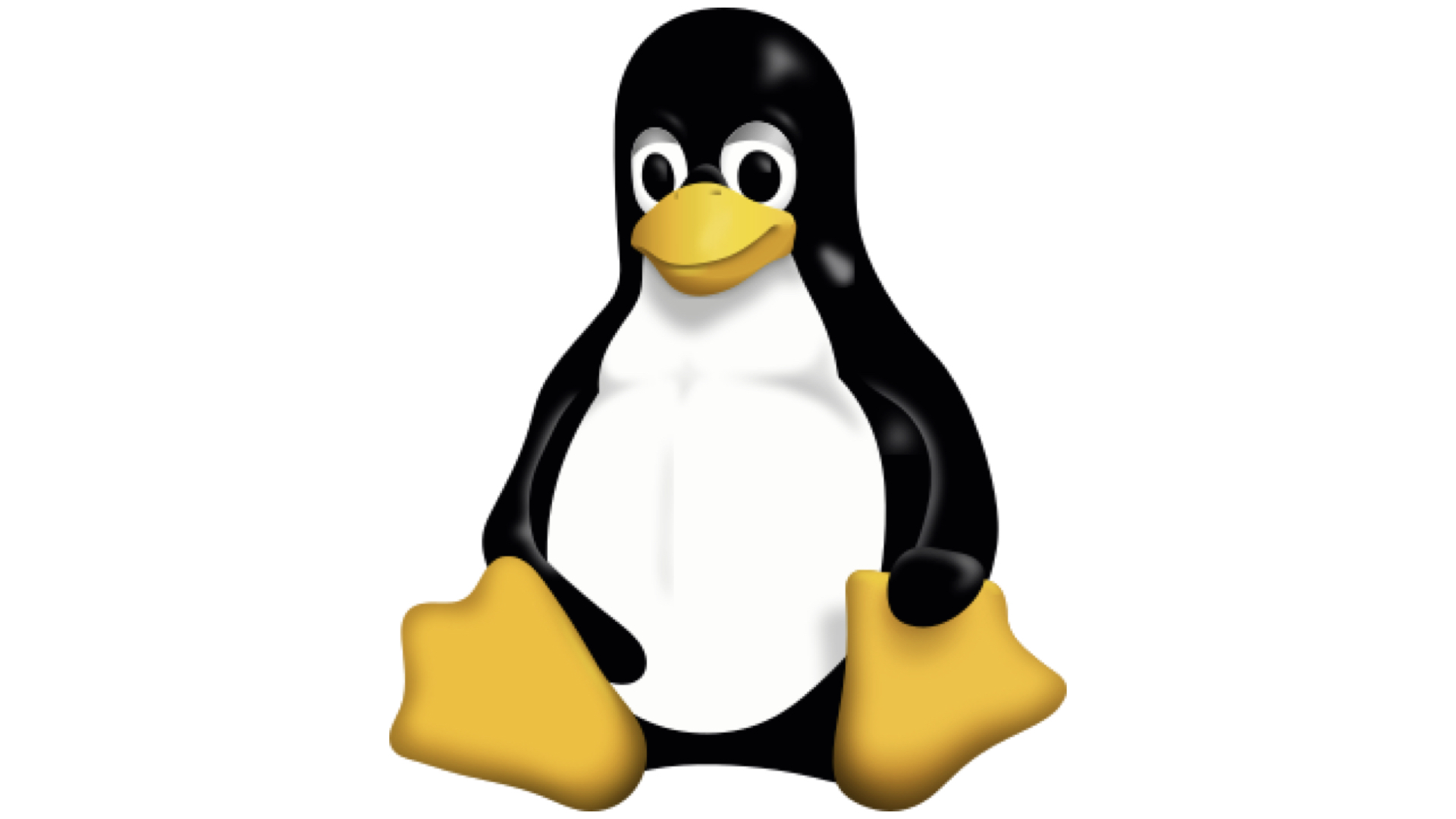


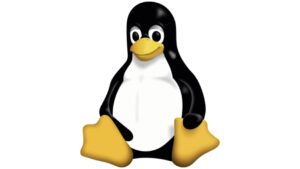
コメント